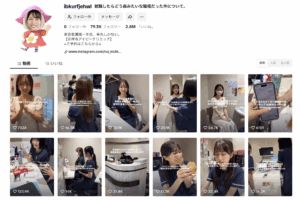【SNS採用の成功事例 Vol.1】株式会社ニトリ

SNSで採用を強化したい中小企業、本当に増えていますよね。

こんにちは!中小企業診断士の西村です。
公的機関で中小企業から相談対応を受ける中で、本当に多いのが「SNS」に関する相談です。
「今はSNSって言うよね。でもどうすればいいかわからない」
「とりあえずインスタ始めて見たんだけど、最近は更新していない」
このように、「とりあえずSNSは身近だから知っているけど、やり方がわからない、続かない」という状況に陥っている中小企業は本当に多いです。この記事に辿り着いた方も同じようなお悩みを抱えているかと思います。
相談に来た方にまず確認するのが「目的」です。つまり、SNSを通じて何を実現したいのか(採用活動の応募を増やしたいのか?お店に来るお客さんを増やしたいのか?自社商品のブランドを発信したいのか?)が迷子のまま「なんとなく」始めてしまっている中小企業の経営者がほとんどです。
この質問をすると、改めて社長が考え出すのですが、採用や離職率低下など「組織内の人事に関する悩みを解決したい」というところに辿り着くことが多いです。つまり、中小企業の中で「採用」にSNSを活用したいというニーズが本当に多いということです!
前置きが長くなりましたが、公的機関などで私に直接相談に来てくださる事業者様には直接アドバイスができるのですが、より多くの中小企業の皆様がSNSを使って採用活動を成功させる確率を高めるために何をしようかと考えた時に、「SNS採用の成功事例をまとめて情報発信しよう!」と思い至りました。
このシリーズでは大手のSNS採用の成功事例を中心に、SNSマーケター×中小企業診断士である私の分析も入れて「中小企業でも参考にできる内容」に落とし込めるような情報を発信していきます。
また、「AIだけでは辿り着けない記事」を目指して情報発信をしていきます。成功事例として単なる生成AIがまとめただけの浅い記事はたくさん転がっていますが、この記事を読んだ中小企業が「SNSにチャレンジしてみよう!」と少しでも思っていただけますと嬉しいです。チャレンジしようと思ったら、ぜひ最後までご覧いただき、何度も繰り返し読んでいただけますと幸いです。
記事が溜まってきたら、YouTubeやTikTokなどでも発信していきますので、ぜひチェックをお願いします!
今回が第1回ということで、まずは「株式会社ニトリ」さんの事例を紹介していきます。
※なお、以下は敬称略で展開させていきますのでご了承くださいませ。
Contents
使用SNSと運用状況を可視化する
株式会社ニトリはInstagramを活用し、就活生や若手人材に対して独自の採用ブランディングを展開しています。
2025年4月現在、ニトリの採用Instagramアカウントは以下のような運用状況です。
・使用SNS:Instagram(@nitorishinsotsu)
・フォロワー数:約7,000人
・投稿数:106件
・投稿頻度:週2回(月曜・金曜)+不定期(土日等)。
※年末年始やお盆など、会社休業期間には1週間ほど投稿なしの期間も見られます。
このように、定期的かつ安定した運用体制が確立されているのが大きな特徴です。特に月・金の定期投稿というスタイルは、「フォロワーが定期的に覗きに来る」行動を習慣化させるうえでも有効な方法といえるでしょう。
私はレコード会社や大手酒蔵でいわゆる「SNSアカウントの中の人」を何度も経験していて実感しているのですが、投稿ペースが週2回というのは、社内で無理なく継続可能なリズムです。これも中小企業が再現しやすいポイントの一つです。というのも、週3で回すとなると月〜金稼働の会社にとっては「2日に1回コンテンツを作り社内チェックをもらい投稿」という業務フローになるので、めちゃくちゃ大変になります。アカウント開設初期は週3ペースで始めてもいいかと思いますが、中小企業がSNSを運用する場合は週2ペースを維持し、長く続けるこを意識するのが理想です。続かなかったら効果薄いですからね。
恐らくですが、ニトリも1〜2ヶ月先の投稿スケジュールを作成し、スケジュールに沿って投稿をしていると思います。概ね、スケジュール上の投稿する日付の1週間前に投稿が作成できていれば安心というイメージですね。
投稿コンテンツ徹底解剖
では、実際にニトリはInstagramでどんなコンテンツを発信しているのか?投稿内容をカテゴリ別に整理・分析してみましょう。
フィード投稿①:「ニトリ社員の働く目的」シリーズ
入社3~4年目の若手社員をピックアップし、「働く目的」「描くキャリア」「ニトリを選んだ理由」などを言語化して発信しているシリーズです。
具体的なSNS運用業務として、説明文や投稿内容は同じフレームを使い効率化しています。おそらく、Instagram担当者が、対象社員に「質問内容」と「写真の提供」を納期を設けてメール等で指示を出し、社員から返信がきたらフレームに当てはめて作成し、スケジュール通りに投稿するという流れだと推測されます。
社員に下記のような情報をメールで送ってもらい、情報収集できればこの投稿は再現できます。
○現部署
○働く目的を一言で
○働く目的の構造:
・What(解決したい課題と、課題設定をした背景)
・How(今後の描くキャリアは? 社員に希望部署を宣誓させる)
・Where(数ある企業の中からなぜニトリ?志望動機は再度社員に整理させる。入社前と異なり、実務を経験した入社3〜4年目でちょうど志望動機が整理されてくるころでより志望する社員に働くイメージを掴んでもらいやすくなるのではないか)
・Whom (誰に?を一言で)例:毎日を精一杯生きている全員に向けて
この投稿を行う目的は複数考えられますが、1つは、既存の若手社員に目的を言語化させることで定着率の向上にも寄与しているのではと推測されます。また、応募者目線でも「自分が入社後どうなっていくのか」をイメージしやすい構成です。
まとめると、社員に自社で働く目的を整理させ、発信することで「定着率の向上」「応募者の働くイメージの醸成」という効果が期待できます。従業員の数だけ投稿が確保できますし、コスパの高い投稿アイデアかなと思います。
ただ、中小企業でこの投稿を実施する場合のハードルとして「出演してくれる社員がいない」ということが考えられます。投稿のエンゲージメントを高めるためには「社員の顔出し」は可能な限りやっていきたいです。SNSを活用しようとしている中小企業の、特に地方の中小企業の社長が頭を悩ませている問題として「暗い社員が多いから、出演は無理だろう」という点です。
SNS採用で社員の顔出しが難しい場合の対応策
ここで、「顔出しNG」な社員が多くSNS運用に踏み出せない中小企業に対し、「じゃあどうすればいいか?」という観点でお話しします。社員が顔出しに消極的な場合でも、魅力的な採用SNSを運営する方法はいくつかあります。
段階的なアプローチ
1.徐々に慣れさせる戦略
・まずは名前だけ・シルエットのみの紹介から始める
・後ろ姿や手元だけなど、部分的な登場から始める
・複数人でのグループ写真から入る(個人への注目が分散される)
2.インセンティブの提供
・出演してくれた社員に小さな報酬や特典を用意する
・社内で表彰する仕組みを作る
・出演者向けの特別研修や成長機会を提供する
まずは小さく始めてみようということで、人事担当者を中心に出演していき、社内全体で出演するという風潮・文化を作っていきます。もちろん、最初は社長が出演するのも良いでしょう。そして、「人を動かす」時と全く同じ考え方で「動機づけ」が必要になります。動機づけにあたり、明確なメリットを提示してあげるのが手っ取り早いです。例えば「SNS手当」を給与に付与するとか、「リール動画の○○再生数」「フォロワー数」など、KPI達成状況に応じたインセンティブ付与という成果報酬型でもいいかもしれません。闇雲にSNS採用に手をつけるのではなく、まずは「社内の人間で出演してくれる人」を探すところから始めてみましょう。
顔出し以外の選択肢
1.代替表現の活用
・アバターやイラスト、アニメーションキャラクターでの代用
・社員の趣味や特技を写真で表現(顔は映さない)
・職場環境や仕事の様子を中心に撮影
2.コンテンツの工夫
・社員の「声」に焦点を当てたインタビュー記事
・匿名での「1日のルーティン」紹介
・社員が実際に使用している道具や制作物の紹介
3.外部の力を借りる
・採用代理店のモデルや俳優の起用
・社員の友人や家族の協力を得る
・内定者や新入社員から始める(若い世代ほどSNS露出への抵抗が少ない傾向)
と、苦し紛れに3点捻り出してみましたが、やはり顔出しできないとなるとSNS採用では結構厳しい情報発信になりますね。魅力的なコンテンツのクリエイティブ力が求められるようになるので、逆に運用が難しくなりそうです。とはいえ中小企業なので中々リソースがない中の意思決定が求められるので、SNS採用に本当に力を入れたいというのであれば、まずは「社長が率先してSNSに出演してみる」という姿勢をみせ、追従する社員を募るという流れが一般的なのかなとも思います。
フィード投稿②:「ニトリ社員の休日」シリーズ
社員のリフレッシュ休暇や趣味の様子を紹介し、「社員のリアルな人柄」や「同期とのつながり」を伝えています。
- 働く環境の魅力だけでなく、ライフスタイルとの両立や社内制度(リフレッシュ休暇)のアピールにもつながっています。
- 社風や人間関係を視覚的に伝えることで、「この会社に入っても大丈夫そう」といった心理的安心感の醸成が期待できます。
フィード投稿③:「ニトリの社員紹介」シリーズ
10~20年目の中堅・ベテラン社員を紹介。配転経歴、やりがい、今後の目標などを深掘りしています。
- 若手だけでなく、中堅層も登場させることで、長期的なキャリアビジョンを描かせやすくなる設計。
- また「どんな上司と働くのか」という情報提供にもなり、ミスマッチ防止や安心感の醸成にもつながっていると考えられます。
その他のフィード投稿
- 内定者/新入社員インタビュー:就活の軸やガクチカ、入社の決め手を明示。リアルな声が学生の共感を誘う。
- 事業部紹介:1日のスケジュールややりがい、今の仕事と過去の経験との接点などを具体的に提示。
- インターン情報・初任給改定・企業説明会告知など、時事性のある情報発信も。
リール投稿
- 部署紹介・ライフイベント(育児)・インターン対談・入社式Vlog風など、動画だからこそ伝えられる“空気感”を重視した設計。
- 特に、「ニトリの噂ウソほんと?」など、学生の不安を打ち消す系コンテンツは興味関心を引きやすく、バズりやすい要素といえます。
ハッシュタグの活用について(※意外と知らない中小企業が多いです)
ニトリは1投稿あたり20個近くタグを設定している投稿もあり、認知拡大には有効ですが、やや多すぎる印象も否めません。
ハッシュタグは「SNS上の本の背表紙」のようなものです。
背表紙はとはどういうことか?あなたが本屋さんの店員になったつもりで聞いてみてください。
「さて、今日もたくさん本が入荷してきたな。陳列がんばるぞ!」
「『5分で簡単!時短レシピ特集』こいつは料理本コーナーに並べれば良いよね」
「『上司に好かれるたった一つの方法』これはビジネス書コーナーかな〜」
「『全旅行好き必見!都内幼稚園ランキング徹底解説!』…??なんだこの本は!!!どこの本棚に並べればいいんだ〜??????」
いかがでしょうか?大分極端に書きましたが、つまりこういうことです。ハッシュタグにごちゃごちゃ入れ込むと、「どこの本棚に並べれば良いかわからない」のです。
これをInstagramのアルゴリズムに置き換えるとどう解釈できるでしょうか。
「Instagramのアルゴリズム=本屋の店員」とイメージしてください。
本屋の店員は、仕入れた本をできるだけ売りたいですよね。そのために、その本に興味がある本棚に仕入れた本を陳列しますよね。だから、背表紙にわかりやすいタイトルがついていたら、適切な本棚に並べてくれて、その本に興味がある人に確実に届けることができるわけです。
Instagramのアルゴリズムも同様の動きをします。Instagramのアルゴリズムさんからすると、TikTokでもなく、YouTubeでもなく、Instagramにたくさん時間を使って欲しいですよね。そのためにはユーザーの満足度を高める必要がありますよね。満足度を高めるためには、「優秀なアルゴリズム」である必要があります。「おすすめ」でAさんが興味を持ちそうな投稿を確実に届けて、
「さすが、Instagram!俺の好みわかってるじゃねーか」
と思わせたいわけです。Aさんの興味のない投稿ばかり流れてきたら、
「おいおい、全然俺のこと理解してねーじゃんか。やっぱりTikTokだよね」
となってしまうわけです。だから、Instagramの思いとしては、
「ハッシュタグ(=本の背表紙)にわかりやすく書いてくれるなら、適切に興味のある人に投稿を届けてあげるから、みんなちゃんとわかりやすくタグ付けしてね」
「あなたのごちゃごちゃなタグ付きの投稿より、Bさんのシンプルなタグ付けの投稿の方がわかりやすくお客さんに届きそうだから、あなたの投稿はおすすめに出さずに、Bさんをおすすめさせてもらうね」
ということになるんです。
じゃあ何個くらいタグ付けすればいいの!と思うかもしれませんが、一般的には、5個前後の厳選されたタグ設計が理想的です。
(例:#ニトリ採用 #働く目的 #社員紹介 #キャリアプラン #就活生応援 など)
ターゲットは誰?想定される狙いとセグメント
ニトリの採用Instagramを見ていくと、その投稿内容は一貫して「就活中の学生」や「若手人材」を強く意識した設計になっていることが分かります。では、もう少し深くターゲット層を分解し、SNS運用の狙いとともに読み解いてみましょう。
ターゲットは「価値観で選ぶZ世代」
近年の就活市場では、「企業のネームバリュー」よりも「自分らしい働き方」や「共感できる社風」で企業を選ぶ学生が増えています。いわゆる“価値観就活”をするZ世代が主なターゲットと考えられます。
ニトリが重点を置いているのは、下記のような価値観を持つ学生層だと仮説をたてます。
- 「自分の目的を持って働きたい」意識高めの学生
- 「やりがい」や「社会貢献性」を重視する学生
- 「社員のリアル」を重視する慎重派の学生
- ネームバリューだけでは選ばず、企業の中身を重視する学生
つまり、単に“就活している学生”ではなく、「人や目的の共感」で企業を選ぶ層に響くように、投稿内容を設計していることが分かります。人事エリートや若手の社員が中心となり徹底的にペルソナ分析し、採用ターゲットを特定しているのでしょう。さすが大企業のニトリですね。
投稿内容がターゲットに響く理由
例えば「社員の働く目的」や「休日の過ごし方」などの投稿は、単なる待遇面や福利厚生ではなく、“人柄”や“考え方”にフォーカスした発信です。
これは、「企業が何をしているか」よりも「どんな人が、なぜその仕事をしているか」を重視するZ世代の関心にマッチしています。
また、リール動画での「Vlog風」投稿や「ニトリの噂 ウソほんと?」のようなライトなコンテンツは、カジュアルに企業を覗きたい層や、ややエントリーに慎重な層にも親和性が高いといえます。
セグメンテーションの仮説:大きく3タイプに分けられる
ニトリのInstagram戦略から見えてくる主なターゲットセグメントは、以下の3つに分類できます。
| セグメント | 特徴 | 投稿の狙い・切り口 |
|---|---|---|
| ①キャリア志向型 | 成長意欲が高く、目的志向で企業を選ぶ層 | 「働く目的」「社員の声」「やりがい」などの内省・共感型コンテンツでアプローチ |
| ②安心・共感型 | 社風や人間関係の“雰囲気重視”型 | 「社員の休日」「入社後のリアル」「部署紹介」でカルチャーマッチを可視化 |
| ③慎重情報収集型 | エントリー前にじっくり比較したい情報収集型 | 「Vlog動画」「噂解消」「インターン体験談」などの不安払拭・理解促進コンテンツで接点づくり |
採用広報としての狙いは「ミスマッチ防止とカルチャーフィット」
これらの投稿から導き出せる、ニトリのSNS採用における“本質的な狙い”は以下の2点と考えられます。
- エントリー数の拡大よりも、カルチャーフィットした人材を確実に惹きつけること
- 「入社後のリアル」を正直に発信することで、ミスマッチを減らすこと
つまり、ただ“集める”採用ではなく、「選ばれるための採用広報」にシフトしていることが明確です。これはZ世代の志向と非常に相性が良く、結果的に企業の採用効率や定着率にも好影響をもたらします。
このようなターゲティング・セグメンテーションの精度こそ、ニトリの採用Instagramが中小企業にとっても学ぶべきポイントだといえるでしょう。
中小企業でも“再現できるポイント”はココだ!
ニトリのような大手企業が行っている採用広報は「うちの会社じゃ真似できない…」と思いがちですが、実はその本質は「伝え方の工夫」と「継続的な発信」にあります。
ここでは、ニトリの採用Instagramの中から、中小企業でも今すぐ再現可能なポイントを厳選して紹介します。
社員の“リアルな声”を発信する
ニトリの投稿では、「どうしてこの会社を選んだのか」「どんな思いで働いているか」といった“内面”に迫る発信が多く見られました。
★再現ポイント
社員インタビューをテキスト・写真で投稿するだけでもOK!
- 「入社の決め手は何でしたか?」
- 「仕事でやりがいを感じる瞬間は?」
- 「社内の雰囲気はどんな感じ?」
このような簡単な質問で、人柄と企業文化が伝わる投稿になります。動画が難しければ、顔写真+一言コメントでも十分に効果があります。
小さな日常や“人間味”を見せる
ニトリの「オフの過ごし方」や「仕事後の買い物風景」など、いわゆる仕事と関係ない“日常”投稿は、企業を身近に感じてもらううえで非常に有効です。
★再現ポイント
社内イベント・ランチ・雑談風景などを“ちょこっと公開”する
- 「社員のお昼ごはん特集」
- 「社長が差し入れしてくれました」
- 「休憩時間のひとコマ」
こうした投稿は、写真1枚+短文キャプションだけで済むので、負担も少なく、人柄重視の求職者に刺さりやすいです。
採用情報を“見やすく”まとめる
ニトリでは、仕事内容や募集職種について「固定投稿」や「ハイライト」で整理されており、パッと見て必要な情報にたどり着ける構造になっています。
★再現ポイント
募集職種・選考フロー・会社紹介などをハイライト化するだけ!
Instagramには「ストーリーズハイライト」という便利な機能があります。これを活用して…
- 「会社紹介」
- 「職種別インタビュー」
- 「選考の流れ」
といったカテゴリを作れば、情報が整って見える=信頼感がアップします。デザインに凝らずとも、シンプルな文字・写真でも十分機能します。
投稿の“目的”を明確にして続ける
ニトリは「社員の想い」「社風の見える化」「働く目的」など、投稿ごとの“狙い”が明確で、それが全体に一貫性を生んでいます。
★再現ポイント
“誰に向けて、何を伝えるか”を明確にして投稿を設計する
投稿ネタを出すときは、以下のフレームが役立ちます。
| 投稿の意図 | 内容の例 |
|---|---|
| 共感を呼ぶ | 社員インタビュー、入社理由、働く目的 |
| 信頼を得る | 仕事内容の紹介、社内制度の解説 |
| 雰囲気を伝える | 社内イベント、休憩中の写真、オフショット |
| 行動を促す | 説明会告知、エントリー受付中、求人情報 |
これをもとに、月に4〜8本程度でも良いので、目的を持った投稿を継続することが最重要ポイントです。
中小企業こそ「人」を見せよう
中小企業が採用で大手と差別化する最大の武器は「人と文化」です。
広告予算では勝てなくても、想いのこもった一枚の写真、社員のリアルな声は、Z世代に確実に響きます。
「完璧でなくていい」「お金をかけなくていい」
その代わり、「人が見えるSNS」を一歩ずつ育てていくことが、中小企業の採用成功につながっていくのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、ニトリのSNS採用戦略を徹底的に分析しながら、「中小企業でも再現可能なポイント」にフォーカスしてお伝えしました。
ニトリのような大手企業の取り組みは、規模の違いこそあれど、コンテンツの考え方や運用体制には「中小企業でも真似できるヒント」がたくさん詰まっています。
特に「社員のリアルな声を届ける」「人間味を出す」「投稿の目的を明確にする」といった部分は、予算やリソースが限られた中小企業こそ強みにできるポイントです。
そして何よりも大切なのは、「やってみること」「続けること」。
SNS採用は、すぐに結果が出る施策ではありませんが、地道に発信を積み重ねることで“自社の魅力を自分の言葉で伝えられる企業”へと育っていきます。
最初は1つの投稿、1人の社員インタビューからで大丈夫です。完璧じゃなくても、まずはスタートを切ってみましょう。
あなたの会社も始めてみませんか?
SNS採用は、始める企業が少ない、始めても途中で諦めてしまう中小企業がたくさんいます。
このブログでは今後も、「中小企業でもすぐ実践できるSNS採用の事例とノウハウ」をたっぷり紹介していきますのでぜひチェックしてくださいね!
採用に悩む企業さまは、ぜひ【リクレマ】のページもチェックしてみてください!
次回の記事もどうぞお楽しみに!