【職務経歴書の書き方】小手先のテクニックでは伝わらない、“選ばれる”差別化戦略
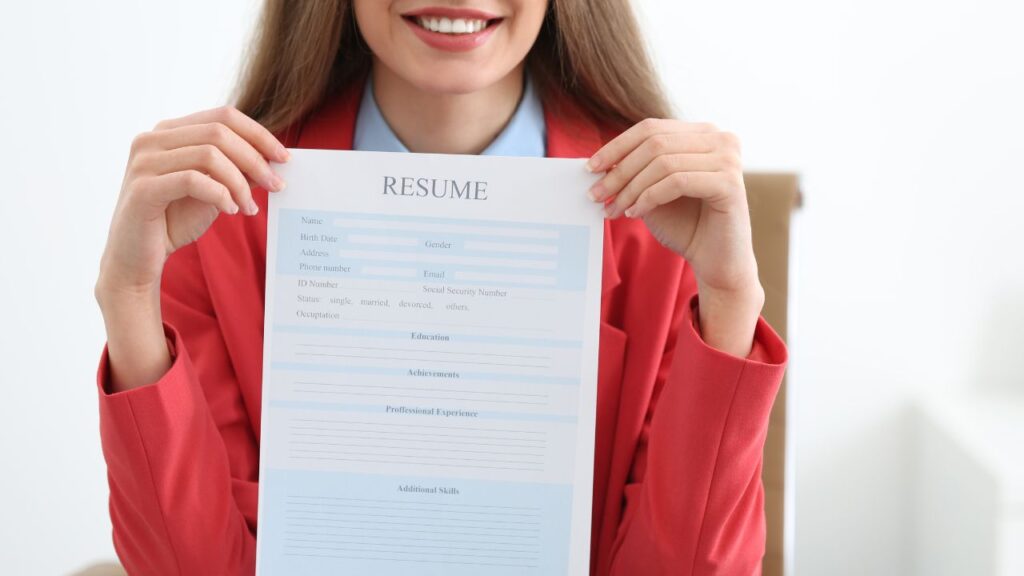
📘 関連記事:
👉 華やかなレコード会社から地方の酒蔵へ。そして経営の世界へ。転職2回で見えた“逆算型キャリア戦略"の本質

“職務経歴書”って結局なにを書けばええんや?
みんな“自己PR”って言うけど、書けば書くほどウソくさくなるやん。

ほんとそれ。特に真面目な人ほど“自分の強み”を無理やり探そうとして、逆に変な文章になっちゃうんだよね。
多くの人が勘違いしているけど、職務経歴書=自分の人生の履歴書ではない。
それは「企業がいま困っていること」に対して、自分がどう貢献できるかを提案する企画書に近い。

企画書?ほな“自分を売り込むマーケティング資料”みたいなもんか?

そうそう。就職や転職って“マッチング”だから、
自分を中心に考えるより、まず相手=企業のニーズを知ることが先。
たとえば、マーケティングでも最初にやるのは「自社の商品説明」じゃなくて、市場分析・競合分析・顧客分析など「外部環境の分析」だ。
転職も同じで、
「自分がどんな人材か」よりも「企業がどんな人を欲しているか」から逆算するのが、本当に伝わる職務経歴書の第一歩になる。

なるほどな。
みんな“ワイはこんなことができます!”ってアピールしてるけど、企業からしたら“それ今いらんねん”って話もあるわけやな。

まさにそれ。
“自分を売り込む”より、“相手にハマる提案”を作る方が、結果的に選ばれる。
この記事では「企業のニーズ」や「他の応募者(競合)」をどう分析し、
そこからどう“自分の見せ方”を設計していくかを、
マーケティング専門の中小企業診断士が具体的に整理していきます。
転職活動中の方、最後までぜひお読みください!
Contents
職務経歴書は“自己紹介”じゃない。企業の課題に答える“提案書”だ

職務経歴書って“自分をアピールする”ってよく言うけど、
それって“企業に媚びる”とか“無理して盛る”ってことなんか?

いや、それとはちょっと違う。
媚びるんじゃなくて、“相手を理解したうえで、自分の何を出すか決める”ってことなんだ。
職務経歴書は「自己紹介」ではなく、企業への提案書。
たとえば、会社が「営業強化したい」と思っているのに、
あなたが「事務処理が正確です」と書いても、いくら正直でも刺さらない。
企業が採用活動をする理由は、
「人が足りないから」ではなく、お給料という形であなたに投資をして「課題を解決したいから」だ。
つまり職務経歴書の目的は、自分の経歴を語ることではなく、
“あなたの課題を、私はこうやって解決できます”を伝えることにある。

ほな、面接官は“お前さんがどんだけすごい人か”よりも、“ウチでどんな課題を解決してくれるか”を見とるってことやな?

その通り。企業が求めてるのは“すごい人”じゃなくて、“フィットする人”。
そして、ここでやりがちなミスがある。
それは「自分の強み」から書き始めることだ。
多くの人がまず「自分には何ができるか」を棚卸しして、
そこから職務経歴書を組み立てようとする。
でも、それは順番が逆。
正しい順序はこうだ👇
1️⃣ 企業のニーズを把握する(どんな人を採りたいのか?)
2️⃣ 競合=他応募者の特徴を想定する(どんな人が応募していそうか?)
3️⃣ そのうえで、自分をどう見せるか(差別化)を設計する

ほぉ〜。つまり自分中心で考えるんやなくて、“相手”中心で組み立てるわけやな。

そう。たとえば“マーケティング職”に応募するとしても、
企業によって“データを分析できる人”がほしいのか、“情報発信できる人”がほしいのかは全然違う。
だからまずは、求人票の言葉や会社HPのメッセージから“その会社の課題”を読み取ることが大事。
「企業の課題を読み取るプロ」である我々中小企業診断士的に言えば、
これはまさに「外部環境分析」から始まる戦略設計。
職務経歴書も同じで、“自分分析”より“企業分析”が先なのだ。

なるほどな。
自己PRは“オレがスゴい”じゃなくて、“お前んとこで役立つオレ”を出せってことやな。

うん。つまり、“自分を語る”より“企業に答える”こと。
職務経歴書は“過去の説明”じゃなくて、“未来の提案”だよ。
職務経歴書を書くときは、まず求人票や企業の採用ページをマーケティング資料として読むこと。
「求める人物像」や「仕事内容」に出てくるキーワードを拾って、自分の経験とつなげる。
この“ニーズと経験のマッチング”を意識するだけで、
書類選考の通過率は一気に上がる。
“ニーズ分析 × 競合分析 × 差別化”で勝つ職務経歴書の作り方

なあお前さん。“企業分析しろ”って言うけど、
正直どこまで調べたらええねん?ホームページ見るくらいで十分ちゃうんか?

まあ、そこまでは誰でもやる。
でも大事なのは、“その企業が今どんな悩みを抱えているか”まで考えることだよ。
たとえば、同じ「エステサロンのマネージャー募集」でも、
ある会社は「店舗を増やしたい」と考えていて、
別の会社は「マネージャーの離職率が高くて困っている」かもしれない。
求人票の“行間”を読むことこそが、ニーズ分析の本質。
🔍 ニーズ分析:求人票の行間を読む
求人票には必ず「この企業がどんな課題を抱えているか」のヒントがある。
たとえばこんなキーワード👇
| 求人票の言葉 | 企業が抱える課題の仮説 |
|---|---|
| 「新規顧客の開拓に力を入れています」 | 既存顧客の売上が伸び悩んでいる/SNS集客が弱い |
| 「チームワークを重視」 | 離職率が高い、または社内連携に課題がある |
| 「主体的に動ける人を歓迎」 | 指示待ち社員が多く、組織が硬直している |

なるほどな〜。表面の言葉をそのまま信じるんやなくて、裏の意図を読むんや。

そう。診断士っぽく言うと、“企業の課題仮説を立てる”感じ。
⚔️ 競合分析:他の応募者と比較してどう見えるか
自分が応募する業界・職種では、どんな人が競合になるかも想定しておこう。
リクナビNEXTやdodaで同職種の求人を見ると、
企業が求めている人物像や共通スキルが見えてくる。
| 競合の特徴 | 差別化の方向性 |
|---|---|
| 若手・ポテンシャル重視 | 実績や即戦力性を打ち出す |
| 業界経験者が多い | 異業界で培った強みを活かす視点を提示 |
| 管理職応募が多い | 現場理解+マネジメントのバランスをアピール |

ほな、他の応募者を“敵”としてじゃなく、“市場データ”として分析するわけやな。

そう。どんな人が応募してそうか想定するだけでも、“自分のポジション”が見えてくる。
🧩 差別化:自分の強みを“相手目線”に翻訳する
ここまで来てようやく、「自分の強み」を出す段階。
でも出し方を間違えると、ただの“自慢話”になってしまう。
たとえば👇
| NG例 | OK例 |
|---|---|
| 「私はリーダーシップがあります」 | 「メンバー3名のチームをまとめ、離職率を半減させました」 |
| 「営業経験が豊富です」 | 「新規開拓を主導し、前年比120%の売上成長を実現しました」 |
| 「企画力があります」 | 「SNSを活用して顧客単価を15%アップさせました」 |

つまり“能力”やなくて、“成果”で語れってことやな。

そう。そして、その成果を“企業のニーズにリンクする形”で書く。
たとえば、求人票に“チームマネジメント経験”と書いてあれば、
“自分がどんな課題をどう解決したか”を具体的にセットで書くのが鉄則。
職務経歴書は「自分の棚卸し」ではなく「相手への提案」。
そのためには、まず外部環境(企業・他応募者)を分析し、自分を相手に合わせて見せる必要がある。
この発想ができるだけで、文章のトーンが自然と「自慢」から「共感」に変わる。
それが、選ばれる職務経歴書の第一歩。
職務経歴書で“嫌われる人”と“信頼される人”の違い

なあお前さん、職務経歴書って“中身”より“印象”が大事って言う人おるけど、
そんなに違うもんなんか?

めちゃくちゃ違う。
実際、内容は似てても“読んでいて気持ちいい人”と“なんか鼻につく人”がいるんだよ。
❌ 嫌われる職務経歴書の特徴
たとえば、こんな文章👇
「私はハーバード大学卒業後、前職で営業として西日本トップの成績を上げてきました。リーダーとしてチームをまとめ、会社に大きく貢献しました。」
一見、すごく良さそう。
でも読む側からすると──
- 「すごいでしょ?」感が強く、共感しづらい
- 自分中心で“企業目線”が感じられない

たしかに。“自分スゴいでしょ”感があると、ちょっと引くな。

そう。企業は“完璧な人”より、“一緒に気持ちよく仕事ができそうな、ウチに馴染みそうな人”を求めてる。
○信頼される職務経歴書の特徴
では、信頼される人の文章はどう違うのか。
「前職では新規顧客の獲得を担当し、リピート率が低いことが課題でした。
SNSでの情報発信を強化し、半年でリピート率を20%改善。
この経験を、貴社の顧客満足向上の取り組みに活かしたいと考えています。」
違いは一目瞭然👇
| 観点 | 嫌われる人 | 信頼される人 |
|---|---|---|
| 主語 | 自分中心 | 企業中心 |
| 書き方 | 能力を主張 | 課題解決を説明 |
| 印象 | 偉そう・自慢げ | 謙虚・誠実 |
| スタンス | 「採用してください」 | 「貢献させてください」 |

自分を売り込む”より、“相手を理解して寄り添う”ほうが強いんやな。

そう。経歴書の中で「企業の課題を言語化」してあげるとより好印象だね。
あと“選ばれる人”って、能力が高い人じゃなくて実は“いい人っぽい人”。
スキルの自慢大会より、文章の温度感で決まる部分が多いんだよ。
転職活動はビジネスの現場でも同じで、
どれだけ優秀でも“感じが悪い人”とは仕事したくない。
採用担当者は、短時間で「この人と働けるか」を判断している。
だからこそ職務経歴書では、成果を語るよりも“姿勢”を伝えることが重要。
「この人なら、ウチの文化になじみそうだな」──
そう思わせたら、書類選考はほぼ突破だ。

結局、採用も“恋愛”みたいなもんやな。
どれだけスペックが高くても自分に合わない人はおるし、素直さが一番やな。

ほんとそれ。完璧より“素直で誠実”。
企業がほしいのは、“能力が高い人”じゃなくて、“一緒に仕事がしたい人”だよ。
結論:職務経歴書は“マーケティング資料”として作れ!

結局のところ、お前さんが言いたいのは“職務経歴書=マーケティング”ってことやな?

そう。
相手(企業)のことを先に理解して、自分という“商品”をどう届けるか。
それが職務経歴書の本質だよ。
💡 マーケティング思考で考える職務経歴書
職務経歴書は「書く書類」じゃなく「設計する資料」。
診断士的に言えば、マーケティングの発想が有効だ。
STEP1:ターゲティング(企業ニーズを明確に)
- 求人票・会社HP・社長メッセージなどから「企業がどんな課題を解決したいのか」を読み取る
- 同じ業界の求人を比較し、採用意図を仮説立てする
STEP2:ポジショニング(競合との差別化)
- 他の応募者が出しそうな“ありがちなPR”をリスト化してみる
- その上で、自分の経験の中から“ズラせる要素”を見つける(例:「異業種の成功事例を応用できる」「現場+企画の両面を知っている」など)
STEP3:プロモーション(自分をどう見せるか)
- 「すごい人」ではなく「信頼できる人」を演出する
- 文章のトーンは誠実・シンプル・具体的に

なんだかワイでもトヨタとか受かりそうになってきたわ!
お前さん、ホンマに詐欺師ばりに説得力あるな!

ありがとう?w
職務経歴書のクオリティが採用の入口を決めるから、転職活動において相当重要な要素だよね。
📊 まとめ:採用担当者の視点で考えよう
| 要素 | 自分視点 | 企業視点 |
|---|---|---|
| 職務経歴 | 経歴を紹介する | 課題解決を提案する |
| 自己PR | 自分の強みを語る | 貢献できる強みを示す |
| 成果 | “やったこと”を書く | “成果が出た理由”を伝える |
| 印象 | すごい人 | 一緒に働きたい人 |

結局、“どんな文章を書くか”より、“誰のために書くか”やな。

そう。“自分中心”をやめて、“企業目線”で設計する。
それだけで、職務経歴書は一気に“刺さる資料”になる。
職務経歴書は、あなたのキャリアを整理する“棚卸しシート”ではなく、
採用担当者が「この人に会ってみたい」と思う“プレゼン資料”。
企業のニーズを理解し、競合との差別化を設計し、
自分を“顧客の課題解決者”として打ち出す──
それが、結果を出す職務経歴書の最短ルートだ。

なるほどな。ワイ、就職する気ないけど、これ読んだら転職サイト登録したくなってきたわ。

ほな、リクルートエージェントな!w
📘 関連記事:
👉 華やかなレコード会社から地方の酒蔵へ。そして経営の世界へ。転職2回で見えた“逆算型キャリア戦略"の本質

保有資格:中小企業診断士(国内唯一の経営コンサルティングの国家資格)
合同会社CLEMA 代表
大手レコード会社、日本酒メーカー、経営コンサルティング会社を経て合同会社CLEMAを設立。SNS採用、SNS集客を中心に中小企業の支援している。公的機関でのコーディネーターも行っており、年間300社以上の中小企業の相談対応を行っている。


